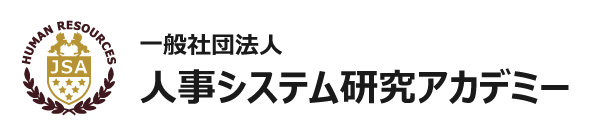活動ブログ
2022.05.11
リードマネジメント拡充事業部会
5月11日(水)17:00より『御馳喜々(ごちきき)』にて開催しました。
議題としては、当事業部が受け持つ来月6月28日(火)の定例会に関する打合せとなります。
LM拡充事業部として、選択理論を学んでいただけるテーマで参加いただけるよう企画しております。
リアル開催を予定していますので、皆様の参加をお待ちしています。


2022.04.24
4月度リードマネジメント研究会
4月度リードマネジメント研究会を
4月22日(金)17時より 県立図書館にて開催しました。
今回のテーマは「承認・評価・フィードバック」
廣野専務理事にお話しいただきました。

参加者は14名

株式会社 i プランニング KOHWA 様では
2年前から、人事評価制度を採り入れ、社員の方に自己評価していただいた上で
年に4回の面談を必ず実施なさっていらっしゃるそうです。(人事制度が完成までに3年を要したそうです)
その制度を採り入れられた目的や経緯、実際にどのように運用なさっていらっしゃるかについて
お話をしてくださいました。
講話後にはグループで、「評価制度について」「評価について」「面談をどのようにしたらよいと思うか」
「明日からどのようなことが実践できそうか」
といったことについて、ディスカッションをしました。


その中でリードマネジメントにおける「自己評価」とはどういうことか
自己評価を促す質問の具体的な方法・フィードバックの仕方についてもお伝えしました。
【ご参加下さった方の感想の一部です】
◎ 評価制度を作られる時の思いが素晴らしい。必ず面談をすると決めていらっしゃるところが凄い。
◎ 社員のみなさんのことを考えられて、一緒に良くなっていこうという思いが伝わっている
◎ 「リーダーになりたい」と言ってもらえる人材を育成されている。自分もそこを目指したい。
◎ 自己評価と評価者からの評価のギャップを埋めることの難しさについてはとても共感した。
◎ 幹部社員を育成する仕組みができていることが素晴らしい。
◎ 自社でも社員がやる気になる制度を作りたい
◎ 社員にジャッジをする制度ではなく、社員の成長を考えた制度にしていきたい
◎ 部下の上質世界に入れるような自分になりたい
◎ 面談 ⇒ 自己評価 ⇒ 自己成長 となる仕組みが大切だと思う
◎ 社員がどんな人になりたいかじっくり聴きたい(人生において・仕事の上で 両方)
◎ どのような面談をすれば社員がやる気になるかを知りたい
廣野専務理事、有難うございました。
お忙しい中、ご参加下さった皆様、誠に有難うございました。
LM拡充事業部 鍵山
2022.03.30
2021年3月会員交流活性化事業部会
会員交流活性化事業部は担当の4月例会について
年度末にもかかわらず、開催しました。
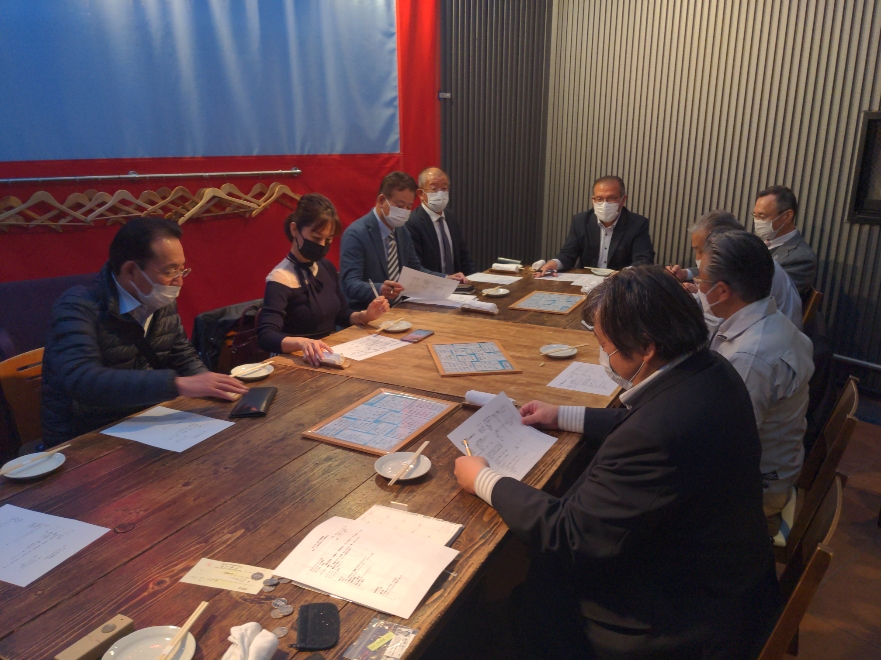
4月例会は、会員の畠真寿美氏による
『生き方が全て「顔」にあらわれる』
です。

懇親会も中身のある例会となりますので
皆様、できればリアル例会でのご参加をお願いします。